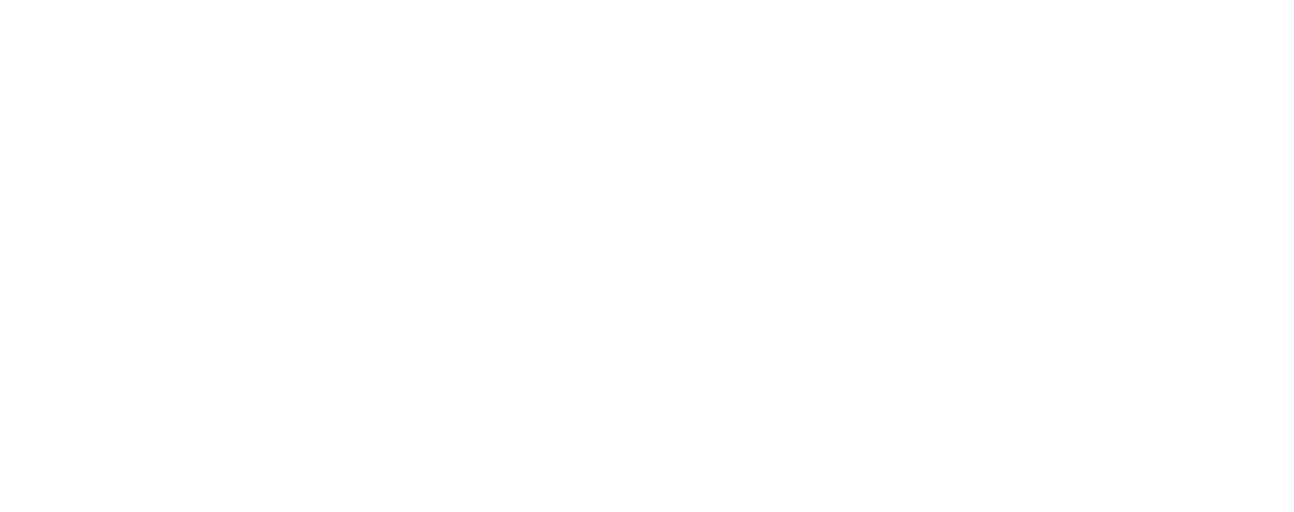Ushimaruのコース料理のハイライトは、なんと言っても炭火焼きのジャージー牛。テーブル越しに眺める火入れのシーンに、否応無く期待が膨らむ。そしてその期待は裏切られない。
まず、ひと口目。肉から滲み出るジューシーなうま味と仄かな甘み。コクのある香味をじっくりと咀嚼しながら辿り、奥行きのある味わいを確かめ、風味の余韻に浸る。
……九十九里の田園に抱かれたこのレストランまで、遥々訪ねて改めて良かったと、心の中で呟く。
「ウシマル」な訳


ジャージー牛の炭火焼きはコースのハイライト。
霧に包まれた九十九里平野、晩秋の夜明け。清らかな朝の空気を抱いた田園は、過ぎゆく秋を名残惜しんでいるようにも見えた。ゆっくりと移り変わる季節の流れの中に、レストランはある。
だが、この日のUshimaruの厨房は定休日にも関わらず、早くも活気に満ちていた。月一回の牛肉の仕入れ日なのだ。ここから車で十数分のところにある食肉センターで枝肉を引き取った後、すみやかに使う部位ごとに解体する。その解体作業のために、早朝からそのセッティングをしていたのだ。
食肉センターに向かう前の準備がひと段落したところでスタッフ一同、コーヒーで呼吸を整える。私も打矢シェフから淹れたてを戴いた。房総内陸の町、大多喜の「珈琲 抱/HUG」で焙煎されたコーヒー豆の一杯は、心地良く全身の細胞を駆動させる。
「うちで使う牛は、基本的にジャージー牛なんです。…じゃ、そろそろ行きますか」
打矢シェフはそう言ってカップを置いて車に乗り込んだ。
そして、その数十分後、食肉センターで目の当たりにしたのは、巨大な牛の枝肉だった。そう、「ウシマル」という店名が示す通り、Ushimaruではジャージー牛をまるごと一頭仕入れているのである。

牛一頭分の枝肉を解体


解体…というよりも、「格闘」という表現の方が、現場感が伝わるかもしれない。
厨房を占拠するジャージー牛の枝肉。既に食肉センターで枝肉にされているとはいえ、巨躯を想起させるのに充分過ぎるほどの大きさである。足腰に踏ん張りをきかせ、全身の力を包丁に集約させる。ベリベリと音をたてながら脂身が剥がされ、やがて電鋸が唸りを挙げ始めた。この日仕入れた肉は250kg以上はあろうかという。
「さっきシェフがやっていたみたいに、枝肉をパッと見て、すぐさま切り始めるというのは凄いことなんですよ」
と、打矢シェフに視線を向けながら語る河野さん。
「自分も2年くらい経ってやっと分かるようになってきたんですけど。牛は母体が大きいので、肉の設計図を頭に入れるのが難しいんです。豚ですとサイズが小さくなるので全体が把握しやすいんですけどね」
厨房へ枝肉を運び込んでから約2時間。ようやく解体作業は佳境に入った。時間を経るごとに、部位ごとに細分化されるその様を目の当たりにして、私は関東地方唯一の捕鯨基地、南房総の和田浦で見学した鯨の解体を思い返していた。命をテーブルへ届ける人たちの真剣さは、海でも陸でも、同じだった。
おいしいジャージー牛を目指して
 食肉センターからの帰り道、隣で車を運転していた河野さんはこんなことも話していた。
食肉センターからの帰り道、隣で車を運転していた河野さんはこんなことも話していた。
「この肉は、いわゆる乳牛のオスなんです。普通ならお乳を出さないから生産性のないものとされちゃうんですけど、シェフがそういうオスの仔牛を引き取りに行って、知り合いの畜産農家に託して育ててもらってるんです。そこは黒毛和牛を育てている方なので、うちの肉は『黒毛和牛と同じ育ち方をしたジャージー牛』って感じになるんです」
ジャージー牛は主に乳牛として飼育される一方で、肉に関しては一般的には市場評価が低く、流通量は少ない。が、実はおいしい。しかもUshimaruのジャージー牛はプロの肥育農家によって育てられているのだ。
さらに、美味しさにはこんな理由も
「1ヶ月から、部位によっては2ヶ月ほど、冷蔵庫で寝かせて熟成をかけます。ですので今月使う牛肉は、先月解体したものがちょうどおいしくなったもの、という感じです」
適切な肥育設計がなされ、部位を見極めながらの解体、そして熟成。それを炭火で絶妙に火入れをして、テーブルへ……。おいしさのリレーは、九十九里平野を舞台に繰り広げられる。

解体を終え、生ハムを作る。塩胡椒をまぶし、牛肉の脂の上部に付いている皮を被せて乾燥や酸化を防ぐ。

こちらは生ハムと焼き芋を合わせたひと皿。肉のうま味とほど良い塩味、そして脂のコクが、とろりとした焼き芋の甘さと見事に溶け合う。

毎週水曜日と木曜日に営業する、普段のUshimaruよりもちょっとライトな食事を楽しめる「CAFE Ushimaru」の人気メニュー「JERSEY BEEF カレー」「JERSEY BEEF バーガー」にも、贅沢にジャージー牛の肉を使う。
「取材・文・写真:暮ラシカルデザイン編集室 沼尻亙司